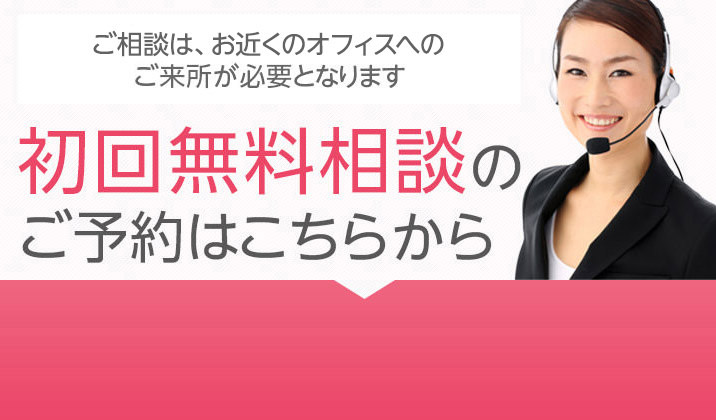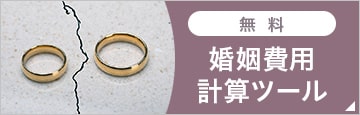有責配偶者から離婚を請求することはできない? 離婚の進め方とは?
- 離婚
- 有責配偶者
- 離婚できない

山形県が発表している人口動態統計によると、山形県では令和4年に1,197組の夫婦の離婚が成立しています。
配偶者との離婚を考えたとき、「有責配偶者から離婚を請求することはできない」と聞いたことがある方も少なくないのではないでしょうか。実際に、裁判で有責配偶者からの離婚請求は原則として認められません。
では、有責配偶者が離婚をしたい場合、どうすれば離婚が認められるのでしょうか? 有責配偶者が離婚する方法や注意点について、ベリーベスト法律事務所 鶴岡オフィスの弁護士が解説します。


1、有責配偶者は離婚請求できない?
有責配偶者とは、婚姻関係の破綻に責任があると認められる配偶者のことを指します。具体的には、不貞行為や暴力(DV)、経済的虐待、育児放棄、配偶者への極端な無関心な態度など、婚姻関係の維持を困難にする行為を行った配偶者が該当することがあります。
民法770条に規定されている法定離婚事由(法的に認められる離婚の理由)は以下の5つです。ただし、④については、令和6年の民法改正(令和6年5月24日公布第33号)により削除が決まっています(施行日は未定ですが、遅くとも令和8年5月24日までには削除される予定です)。
- ① 不貞行為
- ② 悪意の遺棄
- ③ 配偶者の生死が3年以上不明
- ④ 配偶者が強度の精神病にかかり回復の見込みがない(削除予定)
- ⑤ その他婚姻を継続し難い重大な事由
基本的に①~④は⑤の例示にすぎない、と解釈されるのが一般的です。⑤の「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当するかどうかは、個別の事情によって決まります。この「重大な事由」には、暴力(DV)、経済的虐待、育児放棄、配偶者への極端な無関心な態度などが含まれる可能性があります。
また、その個別の事情が「婚姻を継続し難い重大な事由」として認められる程度のものかどうかは、婚姻関係が修復不可能な状態まで破綻しているかどうかによって判断され、この破綻に責任のある配偶者が有責配偶者と呼ばれます。
一般的に、有責配偶者からの離婚請求は、裁判では原則として認められません。これは、離婚原因になる言動で相手を傷つけ、その上さらに相手方配偶者が望まない離婚請求をすることは、信義誠実の原則に反すると考えられているからです。
2、有責配偶者が離婚する方法とは?
有責配偶者からの離婚請求は、原則として裁判では認められません。では、有責配偶者からは絶対に離婚ができないのかというと、そうではありません。
有責配偶者が離婚する3つの方法についてみていきましょう。
-
(1)協議離婚
有責配偶者からの離婚請求であっても、夫婦間協議で相手方配偶者が離婚に同意した場合は、離婚届を市町村役場に提出すれば「協議離婚」が成立します。
そのため、まずは相手に話し合いを求め、離婚条件を相手に有利な内容で提案するなど、誠実に対応して離婚に納得してもらえるように協議を進めていきましょう。
ちなみに、離婚するときに決める必要がある離婚条件の主な項目は以下の通りです。- 親権者
- 養育費
- 面会交流
- 財産分与
- 年金分割
- 慰謝料
たとえば、相手が離婚を拒否する理由が経済的不安の場合は原則半分ずつ行う財産分与(婚姻期間に築いた財産を離婚時に分けること)を相手に多めに行う、養育費を相場より多めに支払うといった提案を行うことで相手の経済的不安を緩和し、協議離婚が成立するように話し合いを進めていきます。
協議が決裂した場合、次に目指すのが「調停離婚」の成立です。 -
(2)調停離婚
相手から離婚への同意を得られず夫婦間協議が決裂した場合、家庭裁判所に「離婚調停」を申し立てます。
離婚調停は、家庭裁判所で調停委員会(裁判官1名と調停委員2名)の仲介を受けながら離婚について話し合い、トラブルの解決を目指す制度です。調停では調停委員会から和解案を提示されたりアドバイスを受けたりしながら話し合いを進めていきます。
ここで相手から離婚への同意を得られれば調停調書が作成され、離婚届と共に市町村役場に提出することで「調停離婚」の成立です。ただし、調停はあくまでも話し合いによってトラブルを解決する制度のため、調停でも離婚が成立しないケースももちろんあります。
調停離婚が成立しなかった場合、有責配偶者が離婚するための最後の方法が「離婚裁判」です。 -
(3)裁判離婚
前述の通り、有責配偶者からの離婚請求は原則として裁判では認められません。ただし、有責配偶者からの離婚請求が裁判で認められる例外があります。
以下のケースに該当する場合、裁判でも離婚が認められる可能性があるでしょう。
① 長期間別居している
有責配偶者からの離婚請求であっても、「長期間別居している」というケースでは、裁判でも離婚が認められる可能性があります。
具体的な別居期間の目安は「10年以上」です。10年以上の別居は夫婦関係が破綻しているとみなされ法定離婚事由の「⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由」に該当し、有責配偶者からの離婚請求でも裁判で認められる可能性があるでしょう。
② 未成熟の子どもがいない
「未成熟の子ども」とは、経済的・社会的に自立していない子どものことです。「未成年」とは異なるため、成人(18歳以上)でも大学に通っている子どもや障害のある子どもは「未成熟子」に該当します。
未成熟の子どもがいない場合も有責配偶者からの離婚請求が認められる可能性があるため、子どもが社会人になっている場合や子どもがそもそもいない場合などに関しては、裁判でも離婚が認められる可能性があるでしょう。
③ 配偶者が過酷な状況におかれない
離婚後に「配偶者が過酷な状況におかれない」という場合も、有責配偶者からの離婚請求が認められる可能性があります。
「過酷な状況」とは、離婚によって精神的・社会的・経済的に追い詰められる状況のことです。
たとえば、配偶者が長年専業主婦(主夫)の場合や、障害のある子どもがいる場合、離婚後に過酷な状況におかれる可能性が高くなるため有責配偶者からの離婚請求は認められません。
しかし逆にいえば、たとえば配偶者が十分に収入を得ており、未成熟子がいないといったケースでは、配偶者が離婚後に過酷な状況におかれる可能性が低いといえます。したがって、有責配偶者からの離婚請求が認められる可能性があるのです。
3、有責配偶者が離婚する場合の注意点とは?
有責配偶者が離婚する場合の2つの注意点について詳しくみていきましょう。
-
(1)別居期間中も婚姻費用の分担義務がある
離婚のための別居期間中も、離婚が成立するまでは婚姻費用の分担義務があります。
「婚姻費用」は、衣食住の費用や医療費、養育費などの生活に必要な費用です。収入の多い配偶者は、収入の少ない配偶者の婚姻費用を負担しなければなりません。子どもがいる場合は、子どもと別居している親に養育費支払い義務があります。
婚姻費用分担義務を怠った場合、裁判で裁判官から不利な判断を下されてしまう可能性もあるため、婚姻費用算定表(家庭裁判所が公表する簡易計算表)を参考に、婚姻費用の金額を取り決めて必ず支払うようにしましょう。 -
(2)相手から慰謝料を請求される可能性がある
有責配偶者は、相手方配偶者から有責行為(不貞行為やDVなど)による精神的苦痛を被った損害賠償として、慰謝料請求される可能性があります。
慰謝料の金額は離婚原因になる有責行為や婚姻期間、子どもの有無などによって異なりますが、離婚する場合の慰謝料相場はだいたい100〜300万円です。
ただし、慰謝料請求の時効が成立している場合は支払い義務がありません。たとえば不貞行為をしていた場合、配偶者が不貞行為の事実と不倫相手を知ったときから3年、不貞行為があったときから20年過ぎると慰謝料請求権が時効によって失われます。
また、相手が有責行為の証拠を示せない場合も慰謝料を支払わなくて済む可能性もあるでしょう。
したがって、仮に慰謝料が請求された場合も、時効が成立しているかどうか、そして証拠があるかどうかは確認することが大切です。また、時効が成立している場合は時効の援用(時効が成立していると主張すること)をしないと時効が成立したことにならないため、時効の援用を必ず行いましょう。
4、有責配偶者が離婚するために、弁護士に相談すべき理由
有責配偶者が離婚するためには、早い段階で弁護士に相談することがおすすめです。
弁護士に相手との交渉を任せることで、ご自身で交渉するよりも早く離婚が成立する可能性が高まります。
また、離婚協議がうまくいかない場合の離婚調停や離婚裁判の手続き・進め方など、離婚を進めるためのアドバイスを受けることも可能です。
さらに、弁護士が入ることで適正な条件で離婚できる可能性も高くなりますので、ご自身が有責配偶者であり相手方配偶者が離婚を拒否している、あるいは拒否される可能性が高いという場合は、まずは弁護士に相談しましょう。
お問い合わせください。
5、まとめ
有責配偶者からの離婚請求は、裁判では原則として認められませんが、だからといって有責配偶者からは離婚が絶対にできないというわけではありません。
夫婦間協議や離婚調停で相手に有利な離婚条件を提示することで、相手に離婚に同意してもらえる可能性があります。
また、長期間の別居や、未成熟子がいないこと、離婚後に配偶者が過酷な状況におかれないといった条件を満たした場合は、裁判でも有責配偶者からの離婚請求が認められる可能性もあるのです。
ただし、別居期間中は離婚が成立するまで婚姻費用分担義務がなくならないこと、そして慰謝料を請求される可能性があることに気をつけなければなりません。
そして有責配偶者が離婚をするためには早めに弁護士に相談することが大切です。その際は、ぜひベリーベスト法律事務所 鶴岡オフィスの弁護士にご相談ください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています
- |<
- 前
- 次
- >|